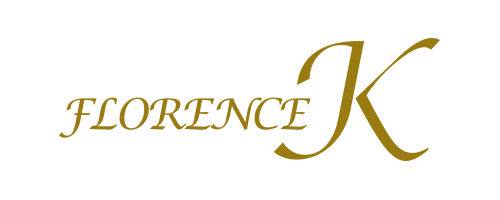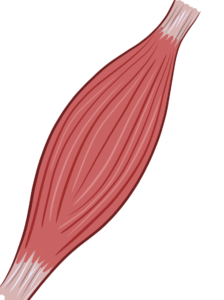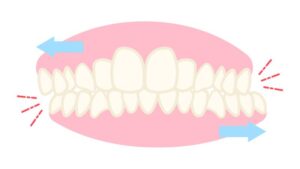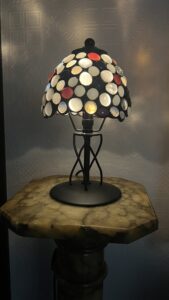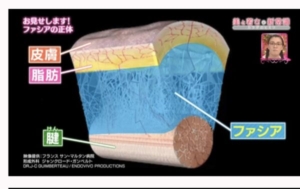こんにちは。静岡市の さとう式リンパケアサロン florence-k です。
夏の暑さが落ち着いてきたのに、だるさや頭が重い感じ、朝起きづらい感じが続いていませんか。
秋バテは水分とミネラルの不足や冷えによる巡りの低下が絡みやすく、飲み物の選び方を少し整えるだけで体がラクになることが多いですよ。
秋バテ 飲み物に関する基本や温かい飲み物の取り入れ方、経口補水液やスポーツドリンクの使い分け、カフェインやアルコールの注意点、冷たい飲み物の影響、常温の活かし方、コンビニで選びやすい実用例まで、わかりやすくまとめます。
- 秋バテ時に心地よく飲めて巡りを助ける飲み物の選び方
- 経口補水液・スポーツドリンク・日常飲料の使い分け
- 温かい飲み物やだし・スープで整える実践レシピ
- コンビニや自宅で今日からできる具体策
秋バテの原因と飲み物の基本戦略

はじめに、秋バテで起こりやすい体の変化と、なぜ飲み物の見直しが効きやすいのかをリンパケアの視点で整理します。全体像が分かると、後半の実践がスムーズです。ここから先は、あなたの毎日に落とし込める形でお伝えしますね。
気温差・冷え・水分不足で「巡り」がゆるむ
秋は一日の寒暖差が大きく、朝晩はヒンヤリ、日中はポカポカという揺れ幅が出ます。
この「振れ幅」が自律神経の切り替えに負荷をかけ、呼吸・血流・消化・睡眠といった身体のリズムがガタつきやすくなるのが秋バテの土台です。
さらに、夏の名残りで冷たい飲み物を続けていると、内臓(特に胃腸)の温度が下がり、
血管や筋肉が強張って「巡り」がゆるみます。
すると、だるさ、頭重感、肩首のこり、手足の冷え、むくみ、食欲のムラ、やる気の低下…
といった症状が連鎖します。
ここ、気になりますよね。
感覚としては「身体のエンジンがかかりきらない」「ブレーキとアクセルを同時に踏んでいる」ような状態。
朝いちの目覚めが重く、日中も集中が続かず、夜は眠りが浅い…という循環に入りやすいんです。
対策の第一歩は、体を冷やしすぎない水分補給です。
冷たいドリンクを一気に流し込むほど胃腸が驚き、消化の働きが落ちやすいので、
常温〜温かいものを「ちょこちょこ」摂るほうが体は喜びます。
汗や呼気からは思いのほか水分が抜けますし、乾いた外気やエアコンの風も水分ロスに拍車をかけます。
秋の空気はサラッとしていて喉の渇きに気づきにくいのも落とし穴。
喉の渇きを感じた時にはすでに軽い脱水に傾いていることもあるので、タイミングを決めて
少量ずつの補給をルーティン化するのがカギです。
さらに、飲み物に「温かさ」と「ミネラル」が加わると、内臓がふっと緩み、体液循環が整い
結果的に呼吸も深くなって気分まで上向きます。
飲み方の方向性はシンプル。
冷やすより、潤して温める。
これが秋バテ対策の土台です。
ポイント:秋は潤しつつ温める方向へ。冷やし続けるより、常温〜温かい飲み物を選ぶだけでも内側の緊張がほどけやすく、朝の立ち上がりや夜の眠りが楽になります。
水・ミネラル・温かさの三本柱
秋バテ対策の飲み物は、成分よりも「設計」で考えると続けやすいですよ。
基本設計は水・ミネラル・温かさの三本柱。
まずベースの「水」は、体液の粘度を保ち、血流とリンパの巡りを助けます。
カフェインや糖分のないシンプルな常温水・白湯・ノンカフェイン茶を土台にしましょう。
次に「ミネラル」。汗や尿と一緒にナトリウムやカリウム、マグネシウムなどの電解質も失われます。
水だけを大量に飲むと、体内の電解質バランスが崩れてだるさや立ちくらみを招くことも。
そこで、味噌汁・だし・野菜スープ、海藻や根菜の具材といった「食べる水分」を挟むとバランスが取りやすくなります。
三本目の「温かさ」は、単なる嗜好ではなく、内臓と自律神経へのケアです。
温かい飲み物は胃腸の緊張をほどき、副交感神経を優位にしてくれるので、消化や睡眠の下支えになります。
生姜湯やハーブティー、温かい甘酒(ノンアル)などは「やさしく温める」代表選手。
反対に、日中暑いシーンで冷たいものを完全にゼロにする必要はありません。
量を少なく、口内で少し温度をなじませる、常温と交互に飲む、といったコツで負担を減らせます。
大事なのは「たくさん飲む」ではなく、体に合った温度と電解質のバランスで、こまめに巡らせること。
これが実感を早くします。
- 水は「ちょこちょこ補給」で体液の粘度を整える
- ミネラルは「飲む+食べる」で補い、電解質バランスを崩さない
- 温かさで内臓をゆるめ、自律神経を休ませる
1日の目安とタイミング
「どれくらい・いつ飲めばいい?」に答える実践編です。
体格や活動量、気温で変わるので厳密に決めすぎないのがコツですが、起床直後/午前/午後/入浴後/就寝前の5ポイントでコップ1杯ずつ(150〜200ml目安)を柱にすると過不足が出にくいです。
朝は白湯や常温水で胃腸を起こし、午前〜午後は常温の水やノンカフェイン茶をデスクに常備して、気づいたらひと口。入浴後は汗で失った水分と塩分を補うため、味噌汁やだし、野菜スープを。就寝前は温かいハーブティーで呼吸を深めると眠りがスムーズに。
「一気飲み」より「分割飲み」が基本。トイレが近くなるのが心配な方は、一口をゆっくり口内で温度になじませると吸収されやすく、負担が減ります。
また、デスクワークが多い日は、タイマーを60〜90分ごとに設定して一口飲むリズムを作るのもおすすめ。
運動や外出がある日は、前後にスポーツドリンクや経口補水液をポイント使いします。
(常用は避ける/詳細は後ほど)
なお、数値はあくまで一般的な目安であり、持病や医師の指示がある場合はそちらを最優先してくださいね。
温度:常温〜温かいを基本に
食事以外の飲み物は「冷たすぎない」を合言葉に。
朝と夜は特に内臓が冷えやすく、ここで温かい飲み物を選べるかどうかが一日の体感を左右します。
朝いちの白湯は、消化管をやさしく目覚めさせ、呼吸も深まりやすくなります。
日中は常温の水・麦茶・ルイボスティーなどをマイボトルに。
気温が高い時間帯だけ、氷入りドリンクを少量楽しむのはOKです。
コツは「一気に流し込まない」ことと、「常温飲料と交互にする」こと。
冷えによる腹部の張りや足先の冷えが出る方は、生姜湯や番茶+生姜スライスも有効です。
辛味が苦手なら薄めで十分。
睡眠の質を上げたい人は、就寝1時間前のカフェインレス+温かい飲み物(カモミール、ラベンダー、焙じ茶、白湯など)が相性◎。
アルコールは一見リラックスできても、体温調節と睡眠の深さを乱しやすいので、就寝直前は控えめが安心です。
「温める=汗だく」ではありません。
内臓のこわばりをほどく「ほんのり温かい」をキープするイメージがベスト。
マグを両手で包んでゆっくり香りを吸い込むだけでも、自律神経は落ち着きますよ。
電解質:塩+カリウムでバランス
汗・尿・呼気で失われるのは水分だけではありません。
ナトリウムやカリウム、マグネシウムといったミネラルも一緒に出ていきます。
ここが不足すると、筋肉のだるさ、こむら返り、立ちくらみ、集中力低下などが出やすい。
対策は二段構えで、
①回復用に経口補水液を短期間ポイント使い、
②日常は味噌汁・だし・野菜スープなど「食べる水分」で補う。
スポーツドリンクは運動前後の一時的なサポートに向き、常用するより「水やお茶と交互に」「薄める」などの調整が無理なく続けやすいです。
なお、経口補水液は脱水状態の回復・予防に用いる特別用途食品で、一般的な日常の水分補給用ではありません。
糖質制限など医師の管理が必要な方は、使用前に相談しましょう。(出典:消費者庁「経口補水液」パンフレット(2024年4月30日))
- 発汗が多い・だるさや立ちくらみがある→経口補水液を短期間で使い切り
- 普段は水・お茶+味噌汁・だし・スープで電解質を底上げ
- スポーツドリンクは「運動に合わせて・水と交互に・薄める」運用が吉
今日からできる実践:選び方とレシピ

次に、シーン別に選びやすい飲み物と、自宅・コンビニでの実践法をまとめます。
全部を一度にやらなくてOK。できるところからで十分です。
あなたの生活リズムに沿って「3本柱(朝・日中・夜)」を決めると、続けるのがラクになります。
目的別:秋バテに役立つ飲み物カタログ
以下は私のサロンで提案している「迷ったらここから」リストです。朝・日中・夜・運動時・回復時という代表シーンを押さえ、常温〜温かい・ノンカフェイン中心・必要に応じて電解質の考え方で選んでいます。テーブルは横スクロール対応なので、スマホでも見やすいですよ。
| 目的・シーン | おすすめの飲み物 | 期待できること | コツ |
|---|---|---|---|
| 朝の立ち上がり | 白湯、レモンをひと搾りした常温水 | 胃腸を起こして巡りをオンに、排泄リズムも整いやすい | 熱すぎない温度で、ゆっくり味わう |
| 日中の潤い補給 | 麦茶、ルイボスティー、カモミール | ノンカフェインで負担が少なく、常温でも飲みやすい | 目につく場所に常温ボトルを置くとリマインドになる |
| 冷え・だるさ | 生姜湯、はちみつレモン湯 | 内側からぽかぽか、気分も軽くなりやすい | 甘みは控えめ、喉の様子を見て濃さを調整 |
| 発汗後・軽い立ちくらみ | 経口補水液(短時間) | 電解質を効率よく補い回復を後押し | 常飲は避け、必要なときに使い切る |
| 運動前後 | スポーツドリンク、炭酸水+少量果汁 | 水分と糖・ナトリウムを補助しパフォーマンスを支える | 運動量に応じて「薄める」「水と交互に」 |
| 食事で整える | 味噌汁・だし・野菜スープ | ミネラルと温かさを同時に取り入れられる | 具材に海藻・きのこ・根菜を足して満足度アップ |
| 胃が重い・疲れ | 甘酒(ノンアル) | やさしい糖とアミノ酸で回復補助、少量でOK | 寝る直前は避け、夕方〜夜に温めて少量 |
| 眠りの質を整える | カモミール、ラベンダー系ハーブティー | リラックスのスイッチを助け、入眠をなめらかに | 就寝1時間前に温かくゆっくり飲む |
上記は「全部やる」前提ではなく、自分に合う3本柱(朝・日中・夜)を決めるためのカタログ。迷ったら、朝=白湯、日中=常温麦茶、夜=味噌汁orハーブティーからで十分です。
コンビニでの即戦力セレクト
忙しい日ほどコンビニの力を借りましょう。
基本は常温の水・麦茶・ルイボスティー。冷蔵ケースではなく常温棚をあえて選ぶのがコツです。
発汗が多い日や屋外移動が長い日は、塩入りタブレット+水の組み合わせでもOK。甘い清涼飲料は一時的に元気が出るように感じますが、血糖値のアップダウンでだるさが反動で強まることがあります。
どうしても甘味が欲しいときは、はちみつを少量足したお湯割りなど、負担の少ない形で。
だるさや立ちくらみが出たら、経口補水液の小容量(ボトルやパウチ)を「回復用」に。復調したら、普段の水やお茶へ戻すのが鉄則です。スポーツドリンクは、運動や大量発汗の前後だけ。常飲せず、水と交互に飲む・薄めるなどで調整しましょう。
温かい飲み物が欲しいときは、カップ味噌汁・具だくさんスープが優秀。塩分が気になる方は、お湯を多めにする・一部をお湯に置き換えるなどで調整できます。小さな選択の積み重ねが、午後の集中力と夜の睡眠に直結しますよ。
- 常温棚から水・麦茶・ルイボスティーをチョイス
- 発汗が多い日は塩タブレット+水、回復用に小容量の経口補水液
- 甘い飲料は「少量・食事と一緒・水と交互に」
自宅で簡単に作れる温活ドリンク
台所にあるもので、内側からポカポカ&ミネラル補給は十分叶います。レシピは「簡単・短時間・材料少なめ」が続く秘訣です。
- 生姜湯:すりおろし生姜少量+お湯。はちみつは小さじ1/2から。生姜は辛味が出やすいので、薄めで十分効きます。喉の違和感がある日は少量ずつ
- はちみつレモン湯:レモン少量+はちみつ少量+お湯。疲労感が強い夕方のひと休みに◎。歯のエナメル質が気になる人は、飲んだ後に水をひと口
- だしスープ:昆布や鰹のだしに少量の味噌。海藻・きのこ・根菜を入れると満足感アップ。朝食の汁物としても優秀です
- 甘酒(ノンアル):温めて少量。寝る直前は避け、夕方〜夜に。胃が重い日は薄めにしてゆっくり
砂糖やシロップの入れすぎは、かえってだるさの原因に。甘さは控えめで、素材の香りを楽しむのが秋の正解です。
注意が必要な飲み方・飲み物
「完全にやめる」ではなく「上手に距離を取る」発想でいきましょう。ゼロにできなくても、体がラクならそれが正解です。まず、冷たい飲み物の一気飲みは胃腸の筋肉をキュッと縮め、消化や吸収を落とします。日中暑い場面だけ少量に留め、基本は常温〜温かいに。
次にカフェインのとり過ぎ。コーヒー・緑茶・エナジードリンクは気分を持ち上げますが、過剰摂取は睡眠の質低下と巡りの乱れにつながります。午前中はOK、午後はカフェインレスに切り替えるなど「時間で区切る」工夫が有効です。最後にアルコールののど越し重視。爽快感はありますが、利尿で水分を失い、睡眠の深さも崩しやすいので、同量の水をセットにし、就寝直前は控えめに。
持病や服薬がある方、妊娠中・授乳中の方は、飲み物の選び方に制限があることがあります。自己判断での急な変更は避け、正確な情報は公式サイトをご確認ください。最終的な判断は専門家にご相談ください。
リンパケアと合わせると効きが早い
飲み物の見直しに、やさしいリンパケアを足すと体感がグッと早くなります。おすすめは耳・首・鎖骨周り。
ここはリンパの「合流点」が多く、触れ方次第で呼吸が深まり、内臓のこわばりがほどけ、末端まで温かさが巡ります。力は入れず、なでる・揺らす・触れるだけでOK。
朝は白湯をひと口飲んだら耳たぶをやさしく回し、鎖骨を胸の中心から肩へ向かってスーッとなでます。
昼はデスクで、首を前後左右に小さく揺らして巡りリセット。
夜は入浴後、味噌汁やハーブティーを飲みながら、首筋・鎖骨下・みぞおちをやわらかくなで、深呼吸。
- 朝:白湯を一口→耳たぶをやさしく回す→鎖骨まわりをなでる(1分)
- 昼:常温の水を一杯→首を小さく前後左右にゆらす(30秒)
- 夜:入浴後に味噌汁やハーブティー→首筋をなでて深呼吸(1〜2分)
「強く押さない・こすらない・短時間を毎日」がコツ。飲み物とケアの相乗で、だるさ→心地よい眠り→翌朝の軽さに繋がります。続けるほど体の声が聞き取りやすくなりますよ。
よくある質問(Q&A)
サロンで多い質問をまとめました。迷ったら「温かく・薄味で・少しずつ」が合言葉です。
Q1. 経口補水液は毎日飲んだほうがいい?
結論、毎日の常用はおすすめしません。発汗が多い日や体調不良時など「回復用」に短期間で使い切るのが基本です。普段は水・お茶・汁物で十分。糖や電解質が多めなので、むしろ体調が落ち着いている日常ではバランスを崩すこともあります。体調とシーンに合わせてポイント使いしましょう。
Q2. コーヒーはやめたほうがいい?
やめる必要はありません。1日の量とタイミングを整えるのが現実的。午前はOK、午後はカフェインレス(デカフェやハーブティー)に切り替える、常温水と交互に飲む、といった工夫で睡眠の質を守りながら楽しめます。
Q3. 冷たい炭酸水はダメ?
「まったくダメ」ではありません。食事と一緒に少量、または常温ドリンクと交互にすれば負担は少なくなります。お腹が張りやすい方は、氷抜き・少量・口の中で温度をなじませる、の3ポイントを。
Q4. 具体的に何から始めればいい?
朝=白湯、日中=常温の麦茶、夜=味噌汁orハーブティーの3本柱を今日から回してみてください。これだけで「朝の立ち上がり」「午後のだるさ」「寝つき」の変化を感じる方が多いです。
さらに整えたいあなたへ
飲み物の見直しと、生活リズム・セルフケアを少しずつ足していくと、秋バテからの回復がスムーズです。理解が深まる関連記事を置いておきます。どれも実践のヒントが見つかるはずです。
今日からの実践チェックリスト
- 朝は白湯、夜は温かいお茶に置き換える
- 日中は常温の水・麦茶をデスクに常備する
- 発汗時だけ経口補水液を短時間で使い切る
- 味噌汁・だし・野菜スープでミネラルを補う
チェックが全て埋まらなくても大丈夫。「できた日が増える」ことが最大の成果です。1〜2週間で体の軽さや睡眠の質に手応えを感じる人が多いですよ。無理なく続ける仕組みづくりとして、マグ・ボトル・ティーバッグを見える場所に置く、スマホのアラームを60〜90分で設定する…なども効果的です。
大切なお願い(免責とご案内)
本記事の内容は一般的な健康情報であり、効果・感じ方には個人差があります。疾患や服薬中の方、妊娠・授乳中の方は医師・薬剤師の指示を優先してください。食事制限や治療中の方は自己判断での急な変更を避け、正確な情報は公式サイトをご確認ください。最終的な判断は専門家にご相談ください。
サロンより
秋は「がんばる」より「やさしく整える」季節。飲み物の選び方をほんの少し変えるだけで、呼吸の深さや体の温かさ、眠りの質がふっと良い方向へ動きます。
さとう式リンパケアは、押さない・揉まない・引っ張らないやさしいケア。飲み物とセルフケアのセットで、あなたの「ちょうどいい」を一緒に探していきましょう。
静岡市の さとう式リンパケアサロン florence-k では、オンラインでのセルフケアレッスンもご用意しています。
迷ったらいつでもご相談ください。あなたの秋が、軽く、心地よく過ごせますように。